フミの鋭い声が、混乱する夜の
闇を切り裂いた。
使用人たちはすぐさま
命じられるままに十字架に
括り付けられていた澄音をほどき
地面へと降ろす。
だが
フミの内心は激しく揺れていた。



澄音を下ろせ!


フミの鋭い声が、混乱する夜の
闇を切り裂いた。
使用人たちはすぐさま
命じられるままに十字架に
括り付けられていた澄音をほどき
地面へと降ろす。
だが
フミの内心は激しく揺れていた。



生贄を渡してなるものか……!


フミは冷静さを装いながらも
焦燥に駆られた声で福米屋に
問いただした。



福米屋様、これはいったいどうゆうことでございますか?





…


しかし、長次郎はフミの言葉を
聞いていなかった。
その視線は鷹丸の背中に
釘付けになっていたのだ。
その背後に——
御厄様(おやくさま)の姿があった。
長次郎の顔が一瞬で青ざめ
驚愕の声を上げた。



お、御厄様……!? なぜここに……?


恐れおののくように後ずさる
長次郎とは対照的に
周囲の使用人たちは
不遜(ふそん)な態度を崩さなかった。
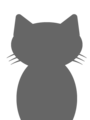


なんだあいつは? もうボロボロじゃねぇか


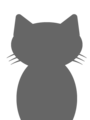


ちょうどいい、まとめて片付けちまおうぜ!


ひとりの使用人が刀を抜くと
それを合図に他の者たちも
次々に武器を手に取った。
そして、一人が叫びながら
鷹丸へと襲いかかる。
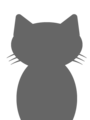


この野郎!





よせ!御厄様に近づいてはならん!


——その瞬間


天地が裂けるような
轟音とともに、雷が十字架へと
直撃した。
燃え盛る炎は雷に煽られ
一層勢いを増し
まるで獲物を貪るかのように
周囲を照らす。
雷鳴の衝撃で地面が揺れ
焚き木が弾け飛ぶ。
使用人たちは恐怖に震え
腰を抜かした。
そんな中、御厄様はゆっくりと
顔を上げ不敵に笑う。



すまんな……力が戻ったばかりで、調整ができぬ


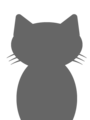


ひ、ひぃぃぃっ!!!


使用人たちは恐れおののき
次々に逃げ出していく。
フミですら後ずさりし
鷹丸の前に立つことを躊躇った。



……絵はいらねぇ
澄音は返してもらうぞ





なぜそこまで……?


雷鳴はまだ遠くで轟いていた。
燃え上がる十字架の火が
闇夜の教会を怪しく照らし続けている——。
これまでのフミの人生には
愛と呼べるものが存在しなかった。
神父に虐げられ
恐怖の中で生き
助けを求めても誰も救いの手を
差し伸べなかった。
祈りは無意味で
世界は冷たく
フミにとって「愛」とはただの
虚構だった。
だからこそ、フミは自らの手で
神父を裁き、自分を守るために
信じられるのは「力」だけだと
信じてきた。
愛を求めることも
信じることも
無駄なことだと切り捨てて生きてきた。
しかし——
目の前のオスの姿に心乱れる。
血に塗れ
朽ち果てようとしながら
それでも愛しき者を救わんと立ち上がる。
鷹丸——その名を持つオスは
神ではなく己の意志で運命を
変えようとしていた。
かつての己と同じように。
されど、決定的に違うのは
彼が愛のために戦っているということ。



馬鹿な……私はもう、何も感じないはずだったのに


ふと、胸の奥が軋む。
信じることを捨てたはずの心が
揺らぎ始める。
神を恨み
愛を知らぬまま生きてきたはずが
目の前の鷹丸の姿に
一抹の希望を見出してしまったのだ。
——愛はすべてを包み
すべてを信じ
すべてを望み
すべてを忍びます
(コリント人への手紙
第一 13:7)
聖書の一節が、まるで耳元で
囁かれたかのように響いた。
震える手を胸に当てる。
心臓が痛いほどに脈打っていた。
鷹丸は疲れ果てた身体を
引きずるようにして
フミの横を静かに通り過ぎた。
視線はただ前を向き
迷いはなかった。
倒れている澄音のもとへ
歩み寄ると
その小さな身体をそっと抱き寄せ
二度と失いたくないものの
ように抱きしめた
その背中は迷いなく遠ざかっていく。
フミはその背中を見つめていた。
鷹丸はただ、
守りたい者を守るために
動いているだけだった。
その強さ、その真っ直ぐな想いが胸を締め付ける。



鷹丸……





——もし、あの小屋で最初に出会ったのが私だったなら
澄音ではなく、私を愛してくれただろうか


雨粒が頬を伝う。
冷たい水滴のせいか
それとも別の理由か
自分でもわからなかった。
ただ
鷹丸の背が遠ざかるにつれ
自分がどうしようもなく
ひとりぼっちになっていくような気がした。
降りしきる雨がまるで罰のように
フミを打ちつけていた。
その頃、教会の中では静かに
別のやり取りが交わされていた。
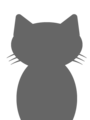


八千代様、生贄がさらわれたようです


付き猫の言葉に
八千代はゆるりと扇を閉じた。
その顔に焦りの色はない。



絵画は無事か?


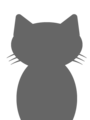


はい





ならばよい。生贄なら、他にもいる


八千代は表情を変えることなく
閉じた扇で窓の外を指し示した。
雨の帳(とばり)の向こう
誰にも縋(すが)れず立ち
尽くすフミの姿を
蛇のような瞳が射抜いていた。
